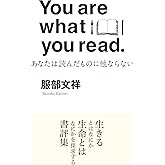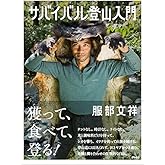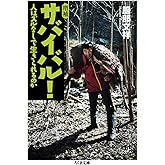無料のKindleアプリをダウンロードして、スマートフォン、タブレット、またはコンピューターで今すぐKindle本を読むことができます。Kindleデバイスは必要ありません。
ウェブ版Kindleなら、お使いのブラウザですぐにお読みいただけます。
携帯電話のカメラを使用する - 以下のコードをスキャンし、Kindleアプリをダウンロードしてください。

百年前の山を旅する (新潮文庫 は 58-1) 文庫 – 2013/12/24
- 本の長さ236ページ
- 言語日本語
- 出版社新潮社
- 発売日2013/12/24
- ISBN-104101253218
- ISBN-13978-4101253213
似た商品をお近くから配送可能
登録情報
- 出版社 : 新潮社 (2013/12/24)
- 発売日 : 2013/12/24
- 言語 : 日本語
- 文庫 : 236ページ
- ISBN-10 : 4101253218
- ISBN-13 : 978-4101253213
- Amazon 売れ筋ランキング: - 291,614位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- - 4,099位新潮文庫
- - 5,969位スポーツ・アウトドア (本)
- カスタマーレビュー:
著者について

ども、はっとりぶんしょうです。アマゾンに宣伝のスペースがあるとのことで、入り込んでまいりました。
6月の下旬にみすず書房から『ツンドラ・サバイバル』(サバイバル登山家シリーズの第3弾)を出すことになり、それのあわせて、いろいろなところでしゃべることになったので、ここで宣伝しておきます(イベント告知のスペースもあるようですが、面倒なので)。6月15日石川県金沢市で夕方(SLANT主催)、7月4日国際ブックフェア。19日湘南ツタヤ(19時から)、7月30日下北B&B、8月8日に群馬県の山の日のフェスにも顔出します。最近「本の雑誌」で連載が始まりました。隔月刊の『フィールダー』でも連載しています。もちろん「岳人」でも連載中です。
月刊「新潮」2月号に創作(小説)が掲載されています。歴史ある文芸誌に掲載していただくという経験全部が面白かったです。作品も苦労した分、なかなかおもしろいものになったのではないかと思います。「ヒロ、青木は登ったぞ」
2014年12月も終わりです。
数年ぶりの単著は『サバイバル登山入門』おかげさまで評判もいいようですが、アマゾンでは品切れが続いていますね。現在、月刊「新潮」2月号に掲載予定の創作の最終ゲラをチェック中です。まともな創作をきちんと発表するのははじめてと言っていいかと思います。よかったら立ち読みしてください。2万字以上あります。『Fielderフィルダー』の19号、12月末発売でも、表紙と中カラー8ページやっています。これは創作とは違いますが、なかなか面白いものになったと思います。他、ビーパル、岳人、などちょこちょこ出ています。岳人は新連載がはじまりました。
以下は2014年4月以前の書き込みです。
「つり人別冊 渓流2014夏」発売されています。3万字以上書きました。ゲラ段階では失敗したかなと思いましたが、できあがったのを読んだら、けっこう面白く書けたなあ、と思いました。
『百年前の山を旅する』が新潮文庫になりました。12月の下旬に発売しています。文庫版あとがきを長々書きました。まだ思いがまとまっていなかったようで、原稿は少し失敗作かもしれません。角幡君が解説を書いてくれました。
『富士の山旅』編集本が河出文庫からでてます。いちおう編者ですが、編集を手伝って解説を書いた編者代表という程度です。他にBE-PALにもときどき出ています。
以下最近の執筆
「つり人別冊 渓流2014春」つり人社(2014/2)連載と新規の短期連載?の二本です。
「BE-PAL2月号」小学館(2014/1)に歩くことに関して寄稿しています。
『白夜の大岩壁に挑む クライマー山野井夫妻 』新潮文庫(2013/8)の解説を書いています。
「現代思想 富士山特集」青土社(2013/9)に寄稿しています。
「ユリイカ 熊特集」青土社(2013/8)に寄稿しています。
『星の王子さまとサン=テグジュペリ ---空と人を愛した作家のすべて』河出書房新社(2013/4)。フランス文学科出身なのですが、この原稿は苦労しました。
『人類滅亡を避ける道―関野吉晴対論集』東海大学出版局(2013/4)のゲストの一人です。
「ユリイカ2012年1月臨時増刊号 総特集=石川直樹」青土社(2011/12)で石川君と対談しています。けっこう面白い話になりました。
『ほかの誰も薦めなかったとしても今のうちに読んでおくべきだと思う本を紹介します。』 (14歳の世渡り術) 河出書房新社(2013/5)
『冬の本』夏葉社(2012/12)。本紹介の単行本です。
「雑誌 広告 2012年11月号」博報堂(2012/10)インタビュー記事ですが上手くまとまったと思います。
「考える人 特集・ひとは山に向かう」新潮社(2011/12)。情熱大陸での事故の話を書きました。
『ハイグレード山スキー最新ルート集』東京新聞(2008/1)共著・編集本です。
『日本の登山家が愛したルート50』東京新聞(2006/4)共著・編集本です。
カスタマーレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中にエラーが発生しました。ページを再読み込みしてください。
- 2020年10月9日に日本でレビュー済みAmazonで購入とても面白くてワクワクしました
- 2020年2月24日に日本でレビュー済みサバイバル登山で有名な著者が、100年前の装備に近いカタチで、
昔のままのルートをたどり、目線・思考を少しでも当時に近づけ、想いを馳せる。
色々と工夫されたクラシックなアプローチで現代の殻を脱ぎ捨てる、結構よかったです。
便利な道具を使って、体験を濃くすることはできない。テクノロジーの持つ
ベクトルはそれと逆に向いている。
凡人はただ、便利な道具で得た余裕の中に安住するだけ。
我々はいろいろなものを手にしてきたが、代わりにスケールを失ってきた、、 とある。
スケールを失う、
交通や通信の発達で、世界は小さくなって、知らないことも少なくなってきている。
また、目先の細かい効率に絡めとられ、悠久に思いを馳せることなどできなくなって
きた現代人の日常の生活にも言えることだと思います。デジタル化が加速してからは
一層、そのように感じます。
- 2013年1月8日に日本でレビュー済みAmazonで購入サバイバル登山家として知られる著者は、高い登山技術と相当な体力をもつ人。これは、ユニークなアプローチでの山遊び?の記録集です。100年前の装備で山に入ったり、ウェストンと嘉門次のように穂高岳に登ったり、鯖街道を一昼夜で歩けるか実験したり、江戸時代の黒部奥山廻りルートを辿ったり・・・。
著者は、それらの山行で「濃い」体験をし、思索を深めています。技術も体力もない私には、マネしたくても絶対不可能。うらやましくてたまりません。
著者が実際にやったように、山奥で、一人で、ライトも持たず、テントもなしで一夜を過ごす。たいていの人には、それすらも怖くて無理でしょう。でも、文明の利器を使わない山歩きは、人を動物としてのヒトに変えていきます。その過程で、私達は確かに「濃い」体験を得られることができそうです。
読んでますます山に行きたくなりました。(でも、ライトは持って・・・)
- 2014年10月6日に日本でレビュー済みAmazonで購入近年、所謂「登山ブーム」の存在が指摘されて久ししいが、人々はなぜ登山という行為に没頭するのだろうか。登山を行う動機は人それぞれであることは言うまでもないだろうが、健康増進のためであるとか自然を楽しむため、あるいは百名山を踏破するため、などといったところが代表的なところではないだろうか。その点、本書に掲載されている山行を著者が行った目的は一味違う。勿論、登山の目的に優劣を付けることなどは出来ないし、する必要も無いのであるが、著者の登山の目的の特異性は評者にとって非常に興味深いものがあった。掲載されている山行の基本的なコンセプトは約百年前前後の登山記録を当時の装備(全てを再現しているわけでは無い)で実際に追体験してみよう、というものである。
中でも、黒部奥山廻りの追体験の節は抜群に出色の出来であると感じた。まず、そのアイディア自体が非常に面白い。その実態が依然として謎につつまれている江戸時代の加賀藩による下奥山廻り(対象とするエリアは後立山の西側一帯)の実態に迫ろうとする山旅であるが、古文書等に基づくルート推定から始まり、実地での検証を丁寧に行っている。ただ、折角掲載されている古地図類が文庫本では全く読み取れず、単なる雰囲気作りにしか役立っていない点が非常に残念であった。また、(これは本書全体に渡って言えることであるが)歩いた軌跡の詳細が不明である(地図は掲載されているが、非常に簡易なものである)ことも価値を減じる要因となっている。
その他の紀行文については、いずれも黒部奥山廻りの追体験には及ばないと感じた。例えば、田部重治と木暮理太郎の奥多摩山行を当時の登山装備で追体験した部分では、彼らの行程を完全にトレースせず、最後は公共交通機関(田部と木暮の自体には存在しなかった)を使って早々と切り上げてしまっている。「当時の山旅を追体験する」のであれば、田部と木暮が歩いた下道もしっかり歩いてほしいものであると感じた。このやや中途半端な切り上げ方が、この山行を安っぽく見える(単に、自己満足のコスプレ登山をしたかっただけではないのか、と思わせてしまう)ものにしてしまっているようにも感じられた。
全体としては、黒部奥山廻りの部分だけでも十分読む価値はあると言える。他の部分については、内容的に今一歩の感が拭えないが、田部重治や木暮理太郎、あるいはウェストンや上條嘉門次といった日本登山界黎明期の偉大な先人達に光を当てている点は評価できる。本書を読むことを1つの契機として、それらの人々について更に調べてみるのはきっと面白いことだろう。著者には、今後更に「著者なりの登山」の探求を進めてもらうことを期待したい。
- 2010年12月31日に日本でレビュー済み100年前の山を想像してみる。奥多摩、北アルプス…未知、未踏のロマンが溢れているはずで…。
でも地図もカッパもヘッ電もなく、今の装備がなけりゃ凄い冒険だよね。
昔の山は面白かったろうなとおもいつつも、ふつうはそこまでなのだが…
服部文祥氏はは登山史を紐解き研究し、ルートをみつけ、それぞれにユニークなテーマで
100年前の山を踏破していく。
スゴイです。
昔はイワナもいっぱいいただろうなあ…。
TVで雪の中をはだしでイノシシを追っかけるシーンを見た友人が、「服部文祥面白い!」と言いました。
- 2010年11月4日に日本でレビュー済み日本の登山史を、服装・装備を含めて再現したという、ユニークな登山体験記でした。今日の日本の登山、特に日本で発展した縦走登山などがいかに出来上がってきたかに思いを馳せることが出来ます。下手な登山史よりも実際に昔と似た条件で歩くことで、100年前の登山をリアルに身近に感じられました。
前作「狩猟サバイバル」では影が薄かった、著者が登山家であることを強く感じることが出来ました。
- 2010年11月5日に日本でレビュー済み著者のサバイバルシリーズももちろん面白いのですが、
もっと山登りを感じられる楽しく、読みやすい作品でした。
日本の登山史に想いをはせられるのもいいです。
- 2013年3月3日に日本でレビュー済みAmazonで購入100年前の紀行文、例えば田部重治の「山と渓谷」、ウェストンの「日本アルプス登山と探検」とかを読んだ方がはるかに面白いです。
著者の意図が本当のところどこにあったのかがよく判らないのですが、少なくとも本の価格には合わない程度の内容だと思いました。
様々な意味でもう少し掘り下げが深ければ良かったのでしょうけれど、なんか著者の単なる自己満足モードだけが残るような読後感でした。